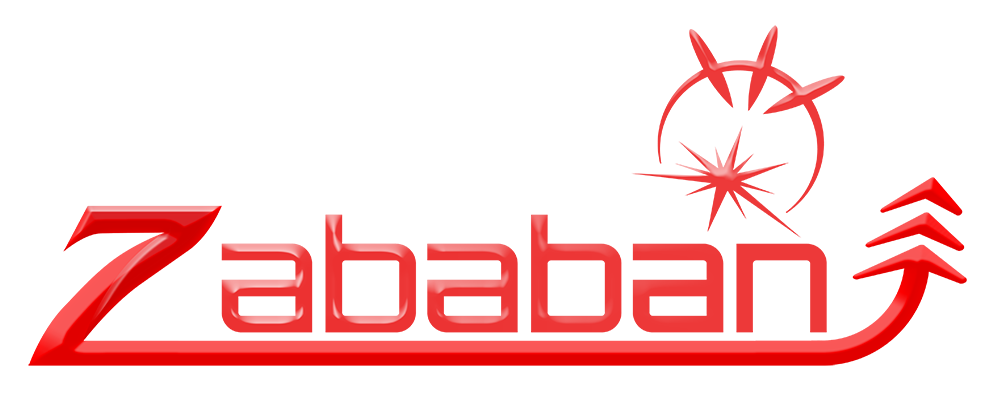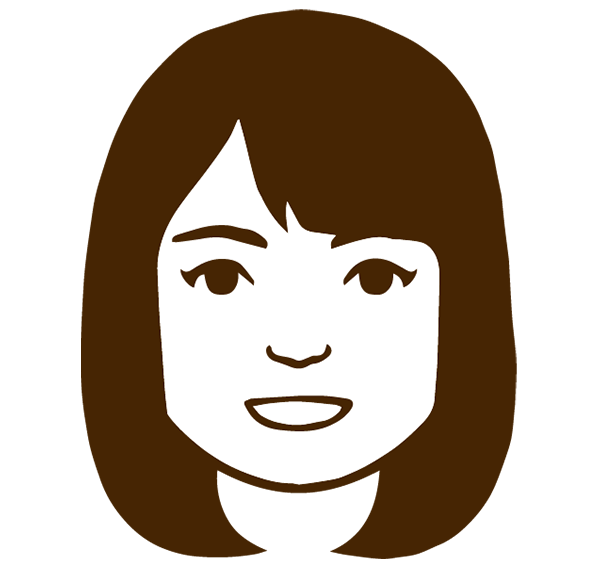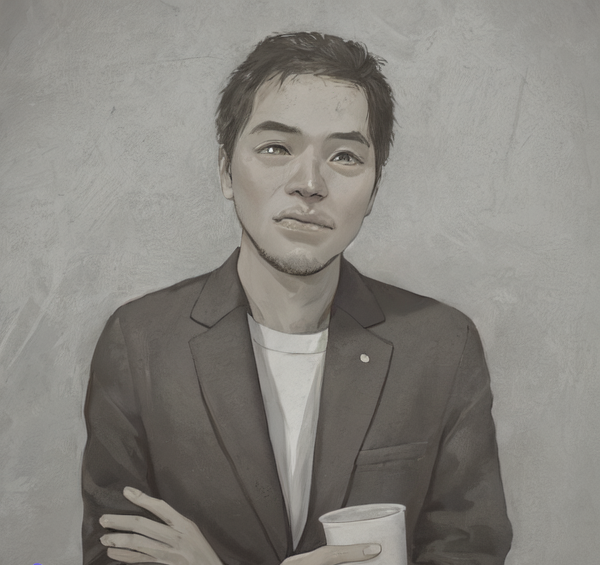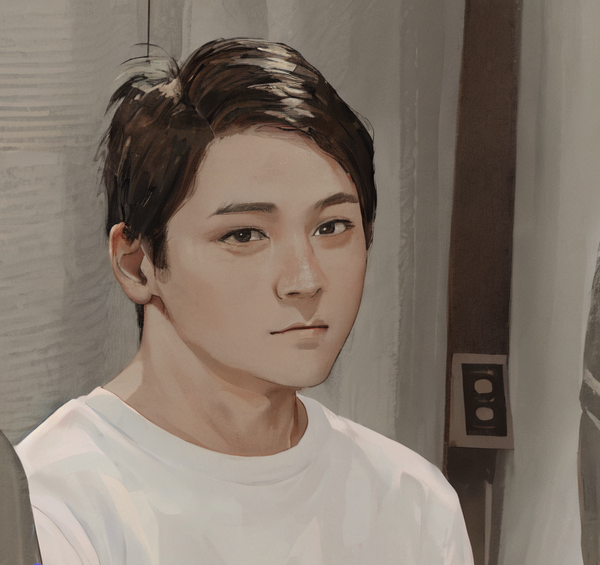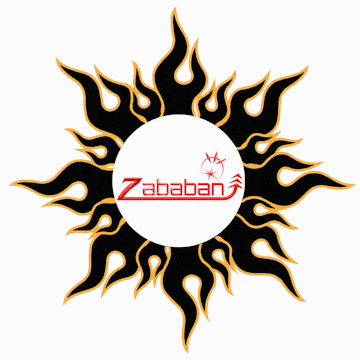

ダイバーシティ&インクルージョンは、「ダイバーシティ=多様性」と「インクルージョン=受容」を組み合わせた考えです。
企業におけるダイバーシティ&インクルージョンの活動や注目される背景について紹介します。
ダイバーシティとは?
ダイバーシティは日本語で「多様性」「違い」を意味します。
企業においては、さまざまな属性の人々が同じ組織の中で働いている状態のことを言います。
私たち人間は一人一人年齢、性別、人種、宗教、障がいの有無、趣味嗜好など異なる価値観やバックグラウンドを持っています。
みんなが同じような属性で、似たような価値観を持っている環境は、一見、揉めごとが起きにくい平和な社会のように思えるかもしれません。
しかし、判断基準や価値観、情報源が似通った人ばかりが集まっている状態は、自ずとそこから生み出されるものも画一的になりやすいといったデメリットがあります。新しいアイデアやイノベーションが生まれにくい環境とも言えるでしょう。
一方、ダイバーシティに富んだ環境では「多様性」や「違い」こそが、強みになります。

インクルージョンとは?
インクルージョンは、日本語で「受容」「包括」「一体性」などと訳されます。インクルージョンの反対語は、日本語で「疎外」を意味するエクスクルージョンです。
インクルージョンとは、誰もが疎外感を感じることなく、自分の強みを発揮できる状態のことを言います。
お互いの個性を認め、一体となって活かし合うこと。エクスクルージョンの対局にある概念です。
背景
日本においてダイバーシティ&インクルージョンが注目される背景には、少子化によって労働人口が減少し、幅広い層から労働力を確保する必要性が出てきたことが挙げられます。
幅広い層から労働力を確保するためには、高齢者や障がいを持つ人などの多様な人材を活用する考え方(=ダイバーシティ)と、それらの人材の能力が発揮できるように組織の一体感を生み出す取り組み(=インクルージョン)の両輪が必要となります。
そのため、ダイバーシティ&インクルージョンという概念が広がっていきました。
さらには、消費者ニーズの多様化もダイバーシティ&インクルージョンの促進が求められる要因の一つです。
従来の働き手だけでは多様化した社会のさまざまなニーズに対応できず、企業としての競争力も低下してしまいます。
こういった課題への対策として、社内に多様な価値観や考え方を持つ人材を雇用する動きも見られます。
ダイバーシティ &インクルージョン推進について
- 優秀人材の確保
- イノベーションの創出
- 企業イメージの向上
- 優秀人材の確保
ダイバーシティ &インクルージョン推進における最大のメリットは、優秀人材の確保ができることです。
ダイバーシティ &インクルージョンの推進によって、 性別や年齢、国籍、障がいの有無にかかわらず、誰もが多様性を認め合い、能力を発揮できる職場環境を実現できます。
こうした環境を整えることで、優秀な人材確保につなげることが可能です。 - イノベーションの創出
イノベーションの創出につなげられることも、大きなメリットです。
同質の価値観を持った集団では、新たな発想が生まれにくく、イノベーションの創出が難しいこともあるでしょう。
しかし、ダイバーシティ &インクルージョン推進によって、多様な価値観を取 り入れられることはもちろん、それらの価値観を融合し、イノベーションの創出につなげること が可能です。 - 企業イメージの向上
企業イメージの向上につながることも、メリットのひとつです。
多様性の取り組みが遅れている日本において、ダイバーシティ &インクルージョンを推進することにより 「先進的な企業」というイメージを訴求することが可能です。
社会的評価の高い企業に属するこ とで、 従業員の帰属意識が高まり、エンゲージメントの向上も期待できるでしょう。

ダイバーシティ &インクルージョンの主な取り組み
- 女性の活躍推進
近年、多くの企業が女性の活躍を目指して、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する取り組みを行っています。これには 『女性活躍推進法』も大きく関わっているといえます。
2022 年の法改正により、常時雇用の従業員が 101 人以上の企業には、女性の活躍推進に関する行動計画の策定や公表が義務化されました。その影響を受け、さらに多くの企業で女性がより活躍 できるような制度を定めたり、職場環境を整えたりといった動きが見られています。
また、これらの取り組みに優れている企業には、厚生労働大臣より認定された「えるぼしマーク」 が送られます。
えるぼしマークを製品や公式サイトに掲載することで、社外へのアピールになるため、企業のイメージアップにもつながるでしょう。
女性の活躍推進の取り組み方法としては、- 女性の採用を強化する
- 女性管理職を起用する
- 育児休暇や時短勤務、在宅勤務などの制度を整える
- シニア人材の継続雇用
これまで日本の企業では、 60 歳を定年とすることが一般的でした。
しかし高齢化が進む現代にお いて、 60 歳はまだ労働力となる年齢といえるでしょう。
2021 年 4 月にから改正施行された『改正高年齢者雇用安定法』の後押しもあり、 60 歳を過ぎた人 も企業の戦力として雇用される機会が多くなっています。
シニア人材の継続雇用の取り組み方法としては、- 70 歳までの定年延長
- 定年後の企業支援
- 定年後の再就職サポート
- 多様な働き方制度の整備
私たちはテレワークを実施し、働き方改革を実現します。
テレワーク への具体的な取り組み方法としては、- 通勤時間の削減やワークライフバランスの改善
- 業務へ集中することができるようになるため、柔軟な働き方が実現
- コミュニケーションをまめにとるように意識改善できる